学校・保護者・地域・行政、みんなで一緒に五條の教育を考えよう!~五條市教育フォーラムを開催しました~
平成27年5月20日(水曜日)市民会館で
五條市教育フォーラムを開催し、教職員や保護者、市民約300人が、これからの五條市の教育について考えました。

太田市長が開会挨拶<要旨>
全国的にも少子化が叫ばれる中、本市においても急激に子どもの数が減少しています。現在そして未来の子どもたちを守るべく、私たちが今やるべきこと、そして今後どうしていくのかという明確なビジョンを持ち、教育を考えていかねばなりません。
社会が目まぐるしく変わる中、現在に応じたかたちの学校の規模、また教育内容の適正化が大変重要になってきました。そうした中、五條市では平成26年5月に「五條市学校適正化検討委員会」を設置し、19名の委員の皆さんに議論をいただいています。(詳しくは学校適正化検討委員会のページをご覧ください。)
今年度は委員会から最終答申をいただき、それを受けて、市民の皆さんの声を聞きながら、地域・学校・保護者・行政が連携をしながら、一緒に五條市の教育を考え、取り組んでまいりたいと考えています。

第一部 文部科学省教育制度改革室の岩岡寛人氏による講演 テーマ:「地域で編む五條市の新たな学校教育」
現在の日本の状況と学校現場・家庭の課題
- 人口減少、少子高齢化、共働き世帯数の推移
- 8割の親が家庭の教育力の低下を実感
- 学習指導要領の改訂で授業時数が増加、学校や教員の仕事は拡大し、多様化している
- 子どもたちは大学進学等で地域から外に出て、そのまま外で就職して戻ってこない現状
国の政策課題
現在の課題を直視し、もう一度薄くなった部分を機織りのように編み直し、積み上げていくことが必要。そのための政策として、縦糸を「小中一貫教育」、横糸を「地域と一体となった学校づくり」として、機織り(学校の小規模化への対応)を行っていく。
小中一貫教育とは
= 小・中学校が目指す子ども像を共有し、9年間を通じた教育課程を編成し、系統的な教育を目指す教育
(※参考 小中連携教育…小・中学校が互いに情報交換や交流を行うことを通じて、小学校教育から中学校教育への円滑な接続を目指す様々な教育)
(背景1)小学校と中学校の違い(学級担任→教科担任、板書スピードが速い、定期テストの有無、生徒指導が厳しい)により、子どもの生活が激変するのではないか。その違いのために小6から中1の間で子どもたちに、不登校・いじめ・暴力行為の増加、学習上の悩み等の問題が生じている。 (背景2)昔に比べて子どもたちの体と心の成長が約2年早まっている。
これらの背景から、小学校と中学校の間をつなぐ小中一貫教育が全国の約1割の学校で取り組まれており、子どもたちの学習意欲の向上、学力向上、自己肯定感の向上などの成果が表れている。(具体的な取組:小中合同行事の実施、9年間で一貫した生活規律、授業規律を実施。9年間で課題克服ができるよう系統立てた授業の実施。)
地域と一体となった学校づくりとは
= コミュニティ・スクールの実施(学校運営協議会。学校の意思決定に地域や保護者の方が加わる仕組みのこと。学校・地域・家庭で教育目標を共有すること。)
小中の縦糸を張るとともに、学校・地域・家庭が同じ目標、方向を揃えて子どもに接することで、子どもたちにしっかりとした価値観を与えることができる。コミュニティ・スクールは横の一貫教育だと言える。
学校の小規模化への対応
日本全体の学校の約50%が、国の学校規模の標準(12学級以上18学級以下)より小さくなっている。全国の75%の市区町村が、学校の適正規模について課題があると認識している。そこで 国は、「公立小・中学校の適正規模・適正配置等に関する手引」を60年ぶりに公表。学校規模適正化の検討は、児童生徒の教育条件をより良くする目的で行うものとして、(1)学校統合による魅力ある学校づくりを行うか、と(2)小規模校のメリットを生かしデメリットを抑え、学校の存続を図るかは、地域に応じて各設置者の主体的判断に任せるとした指針を示した。
学校の適正化を進めるにあたって重視すること
- 学校が小規模であることの課題や、様々な対策の成果をわかりやすく可視化して、関係者間で共有すること
- 学校規模適正化の検討にあたっては、保護者や地域住民にも参画いただくこと
- 児童生徒の保護者や、就学前の保護者の声を重視しつつ、地域で将来ビジョンを共有すること(五條はこういう教育をやっていくんだ、という共通理解を市民で持つことが出発点。)
なぜこんなに学校の適正化が言われるのか
これからは、社会で自立して活動していくための「真の学ぶ力」が必要。知識の習得のみならず、子どもたちが自分で思考して判断しながら、主体的に人とのコミュニケーションを図りビジネスを作っていく能力を身に付けなければならない。そのため国ではアクティブ・ラーニングの充実を進めているが、子どもたちが社会的に自立していくための教育の実現のためには一定の学校規模が必要なため。

第二部 市内の小学生・中学生が夢や志についての意見を発表
- 五條小学校6年生 男子児童
- 阿太小学校6年生 女子児童
- 野原中学校3年生 女子生徒
- 五條西中学校3年生 男子生徒
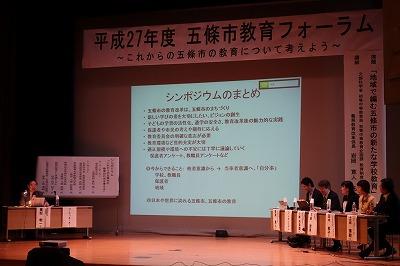
第三部 大学教授や市民代表らによるシンポジウム テーマ:「五條市のこれからの教育を考える」
(コーディネーター)奈良教育大学 名誉教授 重松敬一氏
(シンポジスト)文部科学省初等中等教育局 義務教育係長 岩岡 寛人 氏
奈良教育大学 教職大学院教授 小柳 和喜雄 氏
帝塚山大学 現代生活学部 准教授 元根 朋美 氏
株式会社柿の葉すし本舗たなか 代表取締役社長 田中 郁子 氏
五條市校園長会 会長(現 五條中学校校長) 土田 博敏 氏
五條市の教育改革は、五條市のまちづくり
五條市の教育改革を考えるときには、教育の問題だけではなく、「五條に帰ってきたい」「(外の人が五條を見て)五條に住みたい」と思ってもらえるような、五條市のまちづくりをどうするのかを一緒に考えていく必要がある。
新しい学びの姿を大切にし、ビジョンを創生する
五條市は「こういうことを大事にしているんだ」ということを、きちんと内外に語ることが大事。
子どもの学習の活性化、通学の安心・安全さ、教育改革後に「本当にやってよかった」という魅力を示す、実践すること
子どもたちがその魅力をお互いに語れるようなことを検討していく。
そのためには、保護者や市民の考え・期待をしっかりと踏まえ、応えていけるような教育委員会の明確な意思・方向性を示していく必要がある。
結果、教育環境などの質的充実がはかれていることをきちんと示していく。
適正規模や環境への不安には丁寧に議論していく
改革を進めるにあたって、適正規模や環境への不安があると思うので、それらについては丁寧に議論をしていく必要がある。
すでにお聞きしました保護者アンケートでは、五條市の学校配置の見直しについて3分の1の考えに分かれた。引き続いて教職員アンケートを行っているので、真摯に意見を吸い上げ、それを反映していくことも大事だと考えている。
今からできること=他者意識から当事者意識へ「自分事として」
他者意識(人に任せればよい)ではなく、当事者である意識、自分事として、お互いに考えていただきたい。
市民会館を出た瞬間から、教職員の方々は、今後の五條市の教育はどうあるべきか、どう考えたらよいのかを。保護者の方は、このシンポジウム等の話を踏まえて、近くの方、地域の方々と是非お話をいただきたい。地域でどう学校を支え、また、地域に対して学校がどう協力をしていただけるのかというお話を深めるきっかけにしていただきたい。
日本や世界に誇れる五條市、五條の教育へ
日本や世界に誇れる五條市、五條市の教育の魅力というものを、引き続き皆さんと一緒に語り、そして実現していければと思います。そのためにこのシンポジウム、本日の教育フォーラムが一助となれば幸いです。

堀内教育長が閉会挨拶
本日は大変長い時間でございましたが、熱心にフォーラムに参加いただきましたこと、心からお礼を申し上げます。
本日のフォーラムの中では、文部科学省教育制度改革室の岩岡係長様から、現在の国の教育の動向・方向について、大変大切なお話をいただきました。特に私は、機織りのように縦軸が「小中一貫教育」で、横軸が「コミュニティ・スクール」だという発想を聞かせていただき、もう一度考えてみたいと強く感じました。
4人の子どもたちの意見発表では、大変素晴らしい思いを作文に綴って、大きな声で一生懸命に発表をしてくれました。大変嬉しく思いました。話をするときに、子どもたちに「緊張してるやろ。お茶を飲んで喉を潤して、しっかり発表してな。」と言いました。4人の子どもたちは「はい!」と大きな声で答えてくれました。そして発表してくれました。この子どもたちに、どんな教育を整えるのか。私は今日のセミナーの答えは、ここだと思っています。
私はシンポジウムを沢山見てまいりましたけれども、本日のシンポジウムではパネラーの皆さんが自分からマイクを取っていただき、自分の意見を熱く語っていただきました。そしてそれをコーディネーターの重松名誉教授が見事にまとめていただきました。大変嬉しく、感無量で幕の陰から聞かせていただいておりました。これからの五條の教育を考えるときに、私は大人のエゴで考えてはならないと確信しました。
今回のフォーラムでは、今後の学校教育に係る適正化が大きなテーマでありました。本市では子どもの数が少なくなったから、適正化を検討するのではありません。5年後、10年後、この子どもたちのためにどんな教育を整えるのか。これが適正化の、大きな目的であります。
(以降省略。続きは、以下のPDFファイルをご覧ください)
リンク
ダウンロードファイル
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会事務局 子ども未来課
電話:0747-22-4001
メールでのお問い合わせはこちら










更新日:2019年01月07日